ゆず(柚子)が豊作です
- 閑香 山田
- 2022年12月21日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年10月28日
_ 2022.12.21 _
こんにちは、東北造園です。
弊社の ゆずの木 にたくさんの実が付きました。

ゆずはたくさん実を付ける表年と、あまり実がつかない裏年を1年ごとに繰返します。
(つまり隔年結果です)
今年は表年だったということですね。

本来は枝を広げて育てることで、実が多く付き、収穫がしやすくなるのですが、
この木は植えてある場所の関係で、枝を上に伸ばすように仕立てられました。
2022年の冬至は12月22日(木)です。
冬至と言えばゆず湯ですよね。
ということで、今回はゆずについてお伝えしたいと思います。
ゆずとは?
中国、日本原産でミカン科ミカン属の常緑小高木です。
ゆずは、日本料理に添えられ、料理を引き立てる存在としておなじみです。
生食では酸味が強いですが、吸口や調味料、ジャムとして使われ、とても人気の高い果実です。
また、ゆずと言えば、爽やかな香り。人気が高く香水になるほど。
ゆずは柑橘の中では栽培が容易です。
自分の花粉で受粉して実がなる自家結実性の植物で、1本で実を付けることができます。
枝には写真のように鋭いトゲがたくさんあります。収穫や剪定の際には注意が必要です。

最近では、トゲのない品種があるので、ベランダや狭い場所で育てる場合は特にトゲのない品種を選ぶことをお勧めします。
開 花 時 期
5~6月
白くて小さな花を咲かせます。

少し厚みのある花びらがコロっと咲いてかわいらしいです。
収 穫 時 期
青ゆず:8月
黄ゆず:11~12月
収穫はトゲに注意して行います。

剪 定 時 期
3~4月
詳しい剪定方法の前に、
ゆずの木の育て方として最も重要なのが、樹形です。
ゆずは幹にまで日をたっぷり当てることで実をたくさん付けるようになります。
そのため、木がある程度育った4年目からは、異なる方向に伸びる太い枝(主枝)を2、3本選び、枝が横に広がるようにロープなどで誘引してあげます。
これまで樹形を気にせず育てた木であっても、主枝を3本以下にし、元気のない枝や徒長枝を切って風通しを良くすることで、幹まで日が当たり実付を良くすることができます。ただし、この場合トゲのある枝の剪定作業となるため注意が必要です。
【剪定方法】
〇1~3年目の若い木は特に剪定する必要はありません。あまりに枝が混み合っていれば間引く程度にとどめ、枝を育てます。
〇4年目以降は、収穫後の3月~4月に冬に伸びた枝に花芽ができているため、それを確認しながら切らないように剪定します。また、「今年実が付いた枝には来年実が付かず、今年実が付かなかった枝に来年付く」を繰り返します。そのため、今年実が付いた枝を切り、今年実が付かなかった枝はできるだけ切らないようにします。これにより風通しや日当たりが良くなり、実付が良くなるだけでなく、病害虫の予防・早期発見にもつながります。
今年は急に寒くなり、湯舟につかる時間がなんとも幸せです。
みなさんも是非、今年の冬至はゆず湯につかって
厄を払い、運を呼び込んでください。
ここで豆知識
『冬至とは』
冬至は、二十四節気の一つで、日照時間がもっとも短くなる日です。
二十四節気(にじゅうしせっき)とは、立春、夏至、大寒など季節を表すもので、1年を約15日間ごとに24に分けられ、季節の移り変わりを知るために用いられます。
冬至とは北半球において太陽の位置が1年で最も低くなり、日照時間が最も短くなる日。
逆に、日照時間が最も長くなる日が夏至。夏至と冬至の日照時間を比べると、北海道の根室で約6時間半、東京で約5時間もの差があるそうです。
日照時間が最も短い冬至を境に太陽が生まれ変わり、陽気が増え始めるとされています。つまり、この日を境に運気が上がると考えられています。
『冬至にゆず湯に入るわけ』
ゆず湯は冬至の日に行う禊(みそぎ)の風習だそうです。
冬至にゆず湯に入るのは、運を呼び込む前に体を清める意味があり、冬が旬のゆずは香りも強く、強い香りには邪気が起こらないという考えがありました。
また、ゆずは実るまでに長い年月がかかるので、長年の苦労が実りますようにとの願いも込められています。










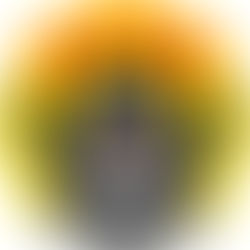
















コメント